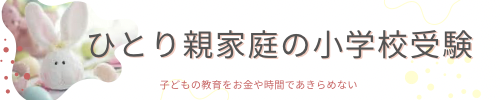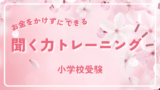国立小学校受験において、巧緻性テストは重要な科目の一つです。毎日の生活が垣間見える試験内容なので、コツコツと続けることが大切です。
しかし、シングルマザーや共働き家庭の方々にとって受験対策の時間を取ることは難しいと思います。私自身、巧緻性の対策方法についてよく知らず時間がかかってしまった時期がありました。
それでもポイントさえ押さえれば、時間がなくても対策できることを知ったので、今回はその内容についてお話ししますね。
まずは、国立小学校受験における巧緻性とはなにか説明します。
巧緻性テストとは
巧緻性テストは、制作や絵画などの課題を通して、子どもの手先の器用さや丁寧さを見るためのテストです。日常生活に関わる内容なので、日々の生活が露骨に出てしまうときもあります。
ただ絵を描けばいいわけではなく、卓上整理や物の貸し借りの仕方なども見られています。
巧緻性テストの出題意図
巧緻性テストでは、発想力や創造力だけでなく、手先の器用さや丁寧さも試されます。家庭での生活の中で対策を行うことが大切です。
単なる技術の習得だけでなく、問題解決能力や集中力、忍耐力なども評価されます。また月齢あわせて、課題の難易度が変化することもあります。
物を大切に扱えているか、物を正しく使えているかなどをチェックされています。幼稚園、保育園や自宅で子どもらしい遊びをしてきたかも重要なポイントです。のりやテープの無駄遣いをしていないか、ハサミの持ち方はあっているかなど基本的な作業ができていることが特に大切です。小学校入学後に授業をスムーズに行うためにも、物を正しく扱えているかどうかを試験では見られています。
また、子どもにとっては難易度の高い問題が出題されることもあります。ここでは物の扱い方はもちろん、集中力や諦めずに頑張れるかどうかも見られています。また、作業途中で試験が終わってもぐずることなく気持ちが切り替えられるかどうかも試験官は見ていますよ。
最後まで作業ができなくても気持ちを切り替えて次の試験に向かわなければなりません。学校によってはあえて作業時間を短く設定して、子どもの気持ちの切り替えを見ているところもあります。
巧緻性と一言では片付けられない、奥深い試験内容ですので、しっかりと対策をされてくださいね。
工作の課題
先生の指示を聞いて、お手本通りに工作をします。ハサミ・のり・テープなどを使い、工作をしていきます。先生のお手本をよく見て、実際に自分で作る必要があるので、いろいろな技術が必要です。ハサミを上手に使えているか、のりやテープを無駄遣いしていないか、ホッチキスの使い方を知っているかなどを確認されます。
「赤色の色鉛筆で塗る」指示があったら必ず赤色の色鉛筆で塗る必要があります。クレヨンで塗ってしまったり、自分の好きな色で塗ってしまうと、指示が聞けていないと判断されてしまいます。減点対象になるので注意しましょう。
丁寧に作業することを意識しすぎて、作業が遅くなってしまう子どももいます。雑な作業も避けたいですが、物をスムーズに扱うことも重要です。
指示を集中して聞くアイデアはこちら
対策
家庭での工作や物の扱いに慣れることが大切です。上手な貼り付け方がわからなくて、のりやテープを使いすぎてしまうことのないように、普段から適量を意識してみましょう。
色付きののりで練習することで、塗っている量が目で見てわかるので使いすぎを減らせます。テープは持ち運びタイプ、卓上タイプ、ハサミで切るタイプ、手で切るタイプなどさまざまなものに触れておくことも大切です。普段使い慣れているものはできても、見慣れていないものだとぎこちない使い方になってしまうからです。
ホッチキス・穴あけパンチ・筆なども工作課題で出ることがあります。特に、ホッチキスや穴あけパンチは握力が足りずに苦戦することもあります。練習が必要な道具でもあるので、普段から意識的に取り入れてみてくださいね。
わが家では、試験2年前から部屋に工作コーナーを作りました。いつでも廃材や工作道具を取り出せるようにして、子どもが好きなときに使えます。また、今まで使っていたおもちゃは押し入れへ片付けました。遊びたいおもちゃがあれば自分で作る!これを徹底したことで、だんだんと作れるものも増えていきましたよ。
最初は好きなように作り、だんだんと小学校受験の内容にあわせた対策をしていきます。簡単な指示から始めて、徐々にレベルを上げていってみてくださいね。
ハサミは特に頻出課題ですので、練習方法はこちらを参考にされてください。
ただ切るだけではなく、線の上の真ん中を通るように切る必要があります。子どもにとってはなかなか難しい作業ですので、コツコツと練習を続けることが大切です。
折り紙の課題
折り紙を使う課題です。指示されたものをとにかくたくさん折る課題や、工作の課題と組み合わさるものもあります。
先生のお手本は1〜2回しかありません。基本的には1回で覚える必要があります。3回しか折らない簡単な指示もあれば、手裏剣程度の難易度のものが出題されることもあるので、対策が必要です。
折り紙の端がきれいに合わさっているか、折筋はきれいについているか、など出来上がりも見られています。折り紙の課題は、普段から慣れ親しんでいるかどうかが上達への分かれ道です。
難しすぎる折り方をマスターする必要はありませんが、手裏剣程度のレベルは折れるようになっておきましょう。
折り紙は図形問題・線対称・展開図などの対策にもなります。子どものレベルに合わせて、どんどん取り入れてみてくださいね。折り紙でできる図形対策はこちら
対策
日常生活で折り紙を使った遊びを取り入れて慣れるといいです。折り紙は持ち運びやすいので、隙間時間にどんどん折っていきましょう。折るだけでつまらない場合は、出来上がった作品でごっこ遊びをすると楽しいです。
折り紙課題のポイントは、角を合わせること、折筋をしっかりとつけることです。
100均も折り紙は販売されていますが、角が合わない場合が多いです。数十円の差で角がしっかりとあう折り紙がありますのでこちらをお勧めします。まずは保護者の方が実際に折ってみて、角が合うかどうか確かめてみてくださいね。表はあっているように見えても、裏があっていない場合もありますよ。
トーヨー 折り紙 創作おりがみ

塗り絵の課題
まる・さんかくなどの塗り絵が出題されます。クレヨン・クーピーペン・色鉛筆・ペンなどさまざまな道具が出題されています。好きな色を塗るのではなく、色が指示されている場合が多いです。
端がはみ出ないこと・塗り残しがないことが採点ポイントです。はみだす部分は5mm以内に抑えた方がいいでしょう。塗り残しがないようにするためには、手首から動かす必要があります。
丁寧に塗りすぎて時間オーバーにならないように気をつけましょうね。
対策
塗り絵を普段から楽しみながら取り入れてみましょう。
塗り残しがないようにする練習は、こすり塗りがおすすめです。紙の下に葉っぱなどを置いて、紙の上から鉛筆などで塗ってみます。塗り残しがない方が葉っぱの葉脈がきれいに浮き出てきますよ。楽しみながらこすり塗りの練習ができます。
こすり塗りができると手首の動かし方も上達していくので、はみ出しも少しずつ解消していくでしょう。
洋服たたみの課題
洋服をたたむ課題です。こちらは普段の生活が見えてくる課題ですので、お手伝いなどで対策していきましょう。ブティック畳みなどもさまざまな畳み方がありますが、国立小学校であればスモック畳みでいいと思います。
服を広げてそのまま折り紙のように折りたたんでいく方法です。洋服店のようにタグがきれいに見える畳み方ではなくて大丈夫です。しかし、難関私立小学校や一部の学校では求める難易度が違いますので、ご自身の志望校の過去問を参考にされてくださいね。
対策
家庭でのお手伝いとして取り入れ、徐々に慣れていきましょう。
お風呂の脱衣所で脱ぐたびに服を畳めば、毎日練習をすることができます。折りたたんだ時にふわっと広がらないようにしてくださいね。靴下をきれいに折りたたむ練習から始めて、徐々にレベルを上げていきましょう。
幼児期に身に付けておきたい手先の巧緻性技術を難易度順に書かれているじぶんでできるかな? 手先の巧緻性点検もおすすめです。
豆つかみの課題
箸を正しく使えているか見る課題です。基本的には豆をつかむ課題が多いです。乾燥した大豆が多く、たまにパスタやビーズなどが出題される場合もあります。
乾燥した大豆はなかなかつかめませんので、それに特化した対策が必要です。箸の練習は小学校受験に関わらず、大切なことです。根気のいる作業ですが、将来のためだと思って頑張りましょう。
対策
箸の使い方を日常生活で練習し、慣れるようにすることが大切です。
箸の練習方法を詳しくまとめた記事がありますので、こちらをご覧ください。
ヒモ通しの課題
ひもをあなに通す課題です。先生のお手本を見て同じように紐を通していきます。指示通りに通していかないと、表側は合っていても裏側がぐちゃぐちゃになってしまいます。
これまでの折り紙や道具の扱い方が上手に扱えていれば、ひもを通すことはできると思います。先生の指示をしっかりと聞き、減点にならないように気をつけてくださいね。
対策
ひも通しの教材はたくさんありますがおすすめはこちらです。
難易度別に出題されているので、子どものレベルや志望校の過去問などにあわせて練習してくださいね。

ヒモ結びの課題
ちょうちょ結び・固結び・縄結びがよく出題されます。工作の指示として組み込まれていることもあり、スムーズに行えることが大切です。
ひも通しよりも難易度が上がり、ひも結びだけで対策が必要です。こま結びで輪っかを作ったり、等間隔に片結びをする課題もあります。
対策
ちょうちょ結びの練習をする際には、2色の紐を用意すると効果的です。自分が今どちら側のひもを持っているか分からなくなっている場合があるので、それを明確にすることができます。
簡単な結び方から始めて、徐々にレベルを上げていきましょう。
盆運び
盆に皿などを乗せて運ぶ課題です。皿だけでなく、水の入ったペットボトルやボールが乗っている場合もあります。
お腹で押さえてバランスをとることのないように、姿勢を正して運びます。
対策
普段の手伝いで練習ができますが、ボールを乗せる練習は別途必要です。志望校によって難易度が変わるので、過去問をチェックしてくださいね。
盆運びの出題が過去にない場合は、ボールを運ぶ練習まではしないていいと思います。
幼児期に身に付けておきたい手先の巧緻性技術を難易度順に書かれているじぶんでできるかな? 手先の巧緻性点検もおすすめです。
お手伝いでできる小学校受験対策はこちら
そのほか
- ぞうきん絞り
- 配膳
- 洗濯ばさみ
- ほうき・ちりとり
巧緻性とは少し離れまずが、上記のような生活に関する作業も出題されます。どれも普段から手伝いをしているかどうかが分かれ道です。
巧緻性テストの3つのポイント
巧緻性テストでは物の扱い方はもちろん、他のことも採点基準になっています。ただきれいな作品を作ればいいわけではありませんので、チェックしていきましょう。
どれも幼児期に身につけたいことばかりですので、小学校受験をしなくても役立つ内容ですよ。
ポイント1: 借り物を丁寧に返せるか
試験中にあつかう資材は基本的に学校側のものです。指定された物を持っていく場合もありますが、学校から用意されるものが必ずあります。
その際に、丁寧に物を返すことが大切です。先生の指示にしたがって片付けをしていきます。指示がない場合も、机の上へきれいにまとめてかた退席しましょう。ハサミが開きっぱなしだったり、ゴミが散乱することのないように卓上整理も大切です。
先生へ物を返すときは「ありがとうございます」と伝えます。
元気よくあいさつをするアイデアはこちら
ポイント2: 教具を譲り合って使えるか
試験ではあえてハサミなどが人数分用意されていない場合があります。子ども同士で物をうまく貸し借りができているかどうかをチェックされています。
作品を仕上げることに必死で、物を独り占めしていては減点対象です。周りの子どもたちとうまく関わりながら、自分自身の作業を進めていくことが大切です。
思いやりを育てる情操教育についてはこちら
ポイント3: 制限時間内で精一杯頑張れるか
試験によっては難易度が高く、制限時間内で終わらない課題もあります。試験には制限時間がありますので、そのあいだは真剣に取り組みましょう。途中であきらめてしまったり、集中力が切れて作業が雑になってしまったりするといけません。
最後まであきらめない気持ちが大切ですよ。
まとめ
巧緻性テストは日常の生活の中で対策を行うことができます。普段の家庭での遊びやお手伝いを通じて、子どもの巧緻性を伸ばしていきましょう。
巧緻性の課題内容は学校によってさまざまです。しかし、求められていることはさほど変わりありません。普段の生活で、「自分のことは自分でできているか」を見られています。幼児期にふさわしい生きる力を身につけるためにも、できるところから始めてみてくださいね。