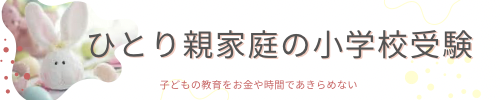箸を使うことは、日本の文化や食事の一部として重要なスキルです。小学校受験でも豆運びが出題される学校もあります。しかし、子どもが箸を上手に使うことは簡単なことではありません。幼い子どもたちはまだ手も小さく、細かな動きをすることが難しいです。そこで今回は、子どもが箸の使い方を上達させる方法について、具体例を交えながらお伝えします。
共働きやシングルマザーの方など、忙しい家庭でもできる内容ですので、気になるところから始めてみてくださいね。
箸の練習のタイミング
箸の練習は早ければいいという物ではありません。
トイレトレーニングのようにその子どもに合ったタイミングがあります。
シングルマザーや共働き家庭の方はなかなか練習の時間が取れないと思います。適切なタイミングを知ることで、よりスムーズに練習が進みますよ。
フォークやスプーンが逆手持ちではない
逆手持ちというのは、1〜2歳ころの子どもがよくするグー持ちのことです。
この持ち方の状態からいきなり箸の練習に入るとハードルが高すぎます。
まずはスプーンやフォークを正しく持てるようになりましょう。
子どもによっては周りの大人の持ち方を見て自然と覚えることもあります。保護者の方のテーブルマナーを見直すきっかけにもなりますので、今一度ご自身の使い方をチェックしてみてくださいね。
グーチョキパーができる
童謡『グーチョキパー』をスムーズに遊ぶことができると手先の力がついてきている目安になります。ピースサインが3本指になってしまったり、蝶々のようにひらひらと指を動かせるようになったりすると手先の巧緻性は上がってきています。
これらのことができるようになるタイミングが重なれば、箸の練習を考え始めてもいいかもしれません。シングルマザーや共働き家庭の方は時間がなかなか取れないかもしれませんが、焦らずできるところから始めてみてくださいね。
子ども用の箸を選ぶポイント
子ども向けの箸には、柄が太いものやエジソン箸のようなものもあります。
しかし、それでは上達が遠回りになってしまいます。箸選びを間違えてしまうと変な癖がついてしまうこともあるので、こちらのポイントをしっかりとチェックしてくださいね。
鉛筆のような六角箸
箸は丸や四角の物が多いですが、六角にすることで手にフィットしやすくなります。一般的な箸よりも細いので間に指を入れやすいです。
鉛筆と同じ六角なので、鉛筆の練習もスムーズにいきます。

手のサイズに合っている
年齢によってサイズが違うので、自分の手に合ったサイズを選ぶことも重要です。
大きすぎると箸同士がクロスしてしまったり、小さすぎると掴む部分が狭くなったりしてしまいます。
こちらのサイトでは手の大きさに合った箸のサイズがわかりますよ。
軽くて滑りにくい箸
プラスチックのように滑りやすい素材は、箸の練習に不向きです。また、重さがあると重心を取ることが難しく、うまく箸を開くことができません。
木製も掴みやすくていいですが、竹でできていると軽さも兼ね備えているのでおすすめです。

箸練習を始める前に
箸は子どもにとってとても難しい作業の一つです。まだ指の力が備わっていないのに始めてしまうと、練習自体が嫌になってしまいます。
食事を楽しむことが優先ですので、まずは指の力をつける遊びを取り入れてみてくださいね。
ねんどあそび
紙ねんど・油ねんど・砂ねんどなんでもいいです!
ねんどを触っているうちに指の力がついてきます。
こねたり、丸めたり、ちぎったり、伸ばしたりする作業は手先をいろいろな方向へ曲げ伸ばしします。その繰り返しが筋力を上げることにつながりますよ。
私自身もシングルマザーで子どもの小学校受験に挑戦をしましたが、ねんど遊びはよくしていました。だんだんと上手になる姿を見るのも楽しいですよ。

おりがみ
折り紙ていねいに折ろうとすると指でしっかりと押さえる必要があります。
指の力が備わっていないと難しい動きです。
ていねいさも一緒に身につきますので、ぜひ取り入れてみてくださいね。
小学校受験の図形問題にも強くなっていきますよ。
シングルマザーや共働き家庭の方はどうしても時間に制限があると思います。一石二鳥の練習方法をどんどん取り入れてみてくださいね。
折り紙はいろいろな方面で役立ちますよ。

手あそびうた
童謡『うさぎとかめ』に合わせて指を交互に出してみたり、グーパーを繰り返したりすることで握力がついてきます。
何も用意せずに、歌うだけでできるので金銭的に厳しいシングルマザーや共働き家庭の方もぜひ試してみてくださいね。
ピンセット運び
指の力がついてきたかなと感じたら、ピンセットを使う練習をしてみましょう。
ピンセットで小さく切ったスポンジやビーズを運ことで、豆運びのような体験をできます。
また、ピンセットでつまむ練習は箸の練習ととても似ているので、スムーズに移行しやすいです。
色分けをすることで小学校受験の指示行動の練習にもなりますよ。

箸の練習アイディア
箸の練習はなかなかうまく進まないこともあります。
いきなり食事の時に挑戦するのではなく、小さく切ったスポンジを掴むところから始めてみましょう。
遊びながら学ぶ
子どもは遊びを通じて学ぶと成長しやすいです。箸を使ったゲームやアクティビティを通じて、楽しく上達させることができます。例えば、箸を使ってビーズをつかむゲームや、箸で小さく切ったスポンジを積む遊びなどがあります。慣れてきたら、カットフルーツを用意して「好きな分だけお箸で入れてね。入った分だけ食べていいよ」とするのも楽しいです。
手のトレーニング
繰り返しにはなりますが、あまりにも上達しない場合は一旦指先トレーニングへ戻ってみましょう。
子どもの成長にあっていない練習は親も子も苦痛になってしまいます。
幼児の手はまだ発達途中であり、細かな動きをするのが難しい場合があります。そこで、手の筋力や指の動きを鍛えるためのトレーニングが重要です。簡単な手遊びや指先を使った工作などを通じて、幼児の手の動きを促進させることができるので、上記の内容を試してみてくださいね。
小学校受験の難問を解く場合もそうですが、その子どものレベルにあっていないものはいくらやっても解けません。レベルにあった練習が大切です。
親子の食事時間
親子で一緒に食事をする時間は、子どもにとって箸の使い方を学ぶ貴重な機会です。家族が箸を使っている姿を見て、子どもは自然に模倣することができます。また、家族との会話や食事の楽しみを通じて、子どもは箸を使うことを楽しいと感じるようになります。
食卓に豆料理を用意することで、食事をしながら豆運びの練習ができます。調理された豆は乾燥したものよりも掴みやすいので、達成感を味わうこともできますよ。
もしお弁当を作る機会があれば、おかずに煮豆を入れてみてはいかがでしょうか。
箸の絵本を読む
絵本好きの子どもであれば、こちらの絵本もおすすめです。
箸の持ち方を口頭で説明をするのは意外と難しいものです。
正しいはしの持ち方を絵と文で教えてくれるので、たのしく覚えることが出来ます。ポイントを押さえた説明と詳細な図解もあるので、保護者の方が説明するときにも役立ちますよ。

辛抱強くサポートする
子どもが箸の使い方を上達させるには、時間と辛抱が必要です。子どもはまだ成長途中であり、失敗を繰り返しながら学んでいきます。そのため、失敗したときには叱らずに、優しくサポートすることが大切です。子どもが自信を持って挑戦できる環境を提供することが、箸の使い方を上達させる秘訣です。
感情的になってしまうとうまくいきません。
目の前の子どものレベルを把握しながら、その子どもに合ったサポートを見つけてくださいね。
これらの方法を実践することで、子どもが箸の使い方を上達させることができます。保護者の方のサポートを受けながら、子どもが自信を持って箸を使えるようになる日を楽しみにしていてくださいね。