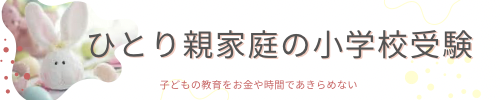小学校受験ではボールを使った課題があります。ドリブル・的当てなどが一般的ですが、どれも練習をしていないと難しいです。
また、運動考査には指示行動も含まれているので、試験官の話すことをよく理解して行動することも求められます。
指示を正しく聞くことも大切ですが、今回は子どものボール上達方法について詳しくお話しします。
ドリブルや的当ては日々の練習の積み重ねが大切ですので、まずはこちらの記事を読んでできるところから始めてみてくださいね。
実際に、ドリブルや的当てが苦手だった子どもが、こちらの方法で少しずつ上達していきましたよ。
ドリブル上達方法
子どもがボールのドリブルを上達させるには、楽しくて簡単な方法を通じて基本的な技術を身につけることが重要です。以下に、子どもがボールのドリブルを上達させる方法をいくつか紹介します。
適切なサイズのボールを使用する
まずは子どもの手に合った適切なサイズのボールを提供します。小さすぎると扱いにくくなりますし、大きすぎるとコントロールが難しくなります。小学校受験を検討されている方はこちらのボールがおすすめです。実際に試験に使われているボールサイズですので、試験対策として有効に使えます。
この時点で、サイズのあっていないボールを使ってしまうと練習が難航してしまいます。
また、せっかくできるようになっても試験当日でいつもと違うサイズのボールが出てきたら戸惑ってしまう恐れもあります。
最初の準びが肝心ですので、こちらはぜひ手に取ってみてくださいね。

基本的なドリブルの動作を教える
基本的なドリブルの動作を教えます。まずは片手でボールを転がすような動作から始め、徐々に両手を使ってボールをコントロールする練習をします。地面に指をついてボールを押す感覚を教えると効果的です。
両手でボールを掴み、おへその位置から落とします。弾んだボールを両手で捕まえます。この動作の繰り返しをスムーズにできるようになったら、片手つきの練習を始めてみましょう。
床にしるしを付ける
ボールをつく際に、あちこちボールが跳んでしまう場合は、床にしるしを付けてみましょう。子どもがどの位置にボールを落としたらいいか分かっていない場合、こちらの方法は効果的です。
その子どものレベルに合わせて床のしるしの大きさは変えてくださいね。迷ったらおおよそ半径10〜15cmほどの円形がおすすめです。
円の中にボールをうまく付けない場合は、両手でボールを真下に落とす練習から始めてみましょう。
両手でリズムよく弾ませることができたら、また片手つきの練習をしてみてください。
目標を設定する
子どもが何かに挑戦をするとき、目標を設定してみましょう。ボールをついた回数をグラフにしたり、できた回数分だけハグをしてみたり。
できたことによる達成感で自己肯定感も育むことができます。
また、口頭試問の内容にも使えますので、記録として残すことはおすすめです。
楽しいゲームや活動を通じた練習
ボールつきの練習はずっと続けていると飽きてしまいます。単純な作業の繰り返しなので、楽しい雰囲気を作り出すことがコツです。
子どもが楽しみながらドリブルの練習を行えるように、ゲームや活動を取り入れます。例えば、音楽に合わせてボールをドリブルしたり、障害物を避けながらボールをコントロールするゲームを行います。
その子どもにあったレベルのゲームで練習を続けることで、少しずつ上達することができます。
まだ片手つきのドリブルがうまくできない場合は、床に3個ほど色の違うしるしを付けてみましょう。音楽をかけているあいだは赤色で両手つき、違う音楽になったら黄色で両手つき、ママが歌い出したら緑の円の中でしゃがむ。
このような動きのあるゲームは子どもが熱中して楽しんでくれます。
保護者の方も楽しい雰囲気を出して、盛り上げてみてくださいね。

手本を示す
大人や兄弟姉妹など、上手なドリブルの技術を持つ人の手本を見せることで、子どもは模倣することができます。手本を見て動作を学ぶことで、子どもの技術向上を促すことができます。
子どものまねる力はあなどれません。
もちろんすぐに上達するわけではありませんが、お手本をみることでコツを掴む場合もあります。YouTubeでもお手本動画がありますので、観てくださいね。こちらは理英会の先生が丁寧に教えていますよ。
積極的なフィードバックと励まし
ボール練習だけでなく、どんなことにも言えることですが、子どもが努力したり成功したりした際には、積極的なフィードバックや励ましを伝えます。子どもの自信を育てることで、ボールのドリブルを上達させるモチベーションを高めることができます。
教える側がつい熱くなってしまい、感情的になることもありますが、そこはグッと堪えてくださいね。叱ってしまうと子どものやる気が続かなくなってしまいます。
子どもの性格によっては闘争心が燃えることもありますが、一度折れてしまった心はなかなか治すkとができません。
少しでもできたことを見つけて、その都度褒める。
これを続けることで練習を続けることができます。
練習を続けないと上達はしないので、とにかく練習を続けるために褒めるのです!笑
余談ですが、わが子は年少のときクラス1番の運動音痴でした。かけっこもいつもビリです。それでも本人は「できている!」と思っていました。私が褒め続けた結果なのか、わが子はとにかく走ることが大好きになりました。結果的に、年長の終わりころにはクラスベスト8に入るように!!
もちろん他の要因もありますが、「走ることが好き」「運動が大好き」と思い続けられたことで上達したと思っています。

ボール投げ・的当て上達方法
子どものボール投げや的当ての上達方法も、楽しさを重視しながら基本的な技術を身につけることが大切です。以下にいくつかの方法を紹介します。
基本的な投げ方の練習
子どもには、基本的な投げ方を教えます。両手を使ってボールを投げるところから始まり、力を込めて的に向かって投げる練習をします。正しい投げ方を教えることで、子どもはより的確に投げることができます。
小学校受験対策におすすめのボールはこちらです。詳しくは、ドリブルのところに記載しています。

的に向かって投げる練習
子どもが的を目指してボールを投げるとき、なかなか的に当たらない場合があります。
的の位置をずらしても当たらない場合は、ボールではなく紙を丸めたものを投げてみましょう。投げるフォームではなく、的に当てることに集中できます。
壁に的を作って、できるだけ近くから丸めた紙を投げます。当たるようになってきたらだんだん投げる位置を遠くしてみましょう。
遠くても当たるようになってきたらボールの出番です。
的には大きなバケツやゴール、マーカーを使うことができます。的に向かって投げることで、子どもは集中力や正確性を身につけることができます。
ゲームで楽しむ
ドリブルの練習でも書きましたが、楽しく練習することが上達の秘訣です。とにかく回数をこなすことで、ボールは上達していきます。
的当てのゲームを通じて投げる技術を上達していきましょう。例えば、的に向かってボールを投げて的に当てるゲームや、的を移動させて動く的にボールを投げるゲームなどがあります。的当てのゲームは楽しさと競争心を刺激し、子どものモチベーションを高めることができます。
手本を示す
ドリブルと同じように理英会がYouTube動画を配信しています。
上手な投げ方をする人の手本を見せることで、子どもは模倣することができます。手本を見て投げ方を学ぶことで、子どもの技術向上を促すことができます。
これらの方法を組み合わせて、幼児のボール投げや的当ての技術を上達させることができます。楽しい雰囲気の中で繰り返しの練習を続けることで、子どもは自然に技術を向上させるでしょう。
自分の体をコントロールすることは、これからの運動能力にも関わっていきます。成長スピードはゆっくりになるかもしれませんが、焦らずできるところから始めてみてくださいね。
子どものボール投げや的当ての上達には、楽しさと練習の両方が必要です。保護者の方は子どもたちをサポートし、子どもが自信を持って取り組める環境を提供することが大切です。失敗や挫折もあるかもしれませんが、そこから学ぶことも大切です。子どもの成長を楽しみながら、ボール投げや的当ての練習を通じて、子どもの運動能力や集中力を育むことができます。そして、その過程で子どもが楽しい思い出を作り、成長していく姿を見守ることができるでしょう。