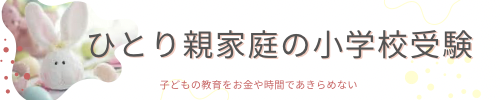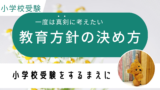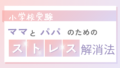子どもを叱ることは、保護者の方にとって避けて通れない場面です。しかし、その叱り方が子どもの自己肯定感に悪影響を与えないようにすることは、非常に重要です。今回は、子どもの自己肯定感を下げない叱り方について考えてみましょう。
わが家の体験談
シングルマザーとして子どもの小学校受験を経験する中で、叱り方について学び成長する機会が多くありました。最初は感情的に怒ってしまうことも少なくありませんでした。
子どもが受験勉強に集中せず、遊んでばかりいる姿にイライラしたり、やる気が感じられない時にはつい感情的になってしまったことがあります。しかし、そのような時には冷静になり、なぜその行動が問題なのかを子どもと共有することを心がけました。
今感情的に叱っても何も特にならない。関係性が悪化するだけだ。と自分に自問自答して怒りを落ち着かせていました。私のその行動が将来にどのような影響を及ぼすのかを想像してみました。また、私自身の目標を立てたり、その都度振り返りをすることで、その場の感情で叱ることが少なくなっていきました。
叱る時には、子どもの目線で話をすることも大切にしました。その方が子どもは叱られたとしても尊敬されたと感じやすく、受け入れやすかったように思います。
また、叱った後は必ずフォローアップをするようにしました。たとえば、「今日は集中できなかったけれど、次はもっと頑張ってみようね」と励ましの言葉をかけることで、子どもが前向きに取り組める環境を作ることができました。
小学校受験勉強のプレッシャーもある中での叱り方は、自己肯定感を損なわずに子どもの成長を促すために欠かせない要素でした。その経験を通じて、子どもとのコミュニケーションや叱り方の重要性を再認識しました。
自己肯定感に関する本をたくさん読みましたが、本質的なことはどれも同じのように思います。子どもの「やってみたい」をぐいぐい引き出す! 「自己肯定感」育成入門 では、幼児期から中学校受験まで活かせるノウハウが具体的に書かれています。アマゾンのAudibleが無料だったので、ぜひチェックしてみてくださいね。
自己肯定感を下げない叱り方
私は幼稚園教諭と保育士と社会福祉士の資格を持っていますが、実際にわが子を目の前にすると感情的に叱ってしまうことがありました。本当に情けない話です。
知識があっても行動に移せないのが人間です。自分の失敗を自覚して、今後に活かすことがとても大切です。巷には自己肯定感についての記事がたくさんありますが、そのうちのどれだけを実行できているでしょうか。
人間は間違えてしまいますが、その間違いを少しでも少なくしていきたいものです。私は、自分の行動を客観視するため、定期的に自身の行動を振り返っていました。実際に紙に書き出し、自己採点もしていました。それらを踏まえて次回の目標設定をしていきます。
まずは、どの項目を自分の目標にするかを決めて、少しずつ意識する項目を増やしてみてくださいね。目標を決めたら、定期的に振り返りもしてみてください。
1. 肯定的な言葉を使う
叱る際に使う言葉は非常に重要です。子どもに対して肯定的な言葉を使うことで、その人格や努力を認めることができます。例えば、「あなたはとてもかっこいいからもっと頑張れるよ」というように、叱りつつもポジティブな方向に持っていくことが大切です。ただし、ただ肯定的な言葉を並べるのではなく、具体的な改善点も一緒に伝えることが効果的です。
肯定的な叱り方は、子どもの成長や自己肯定感を育む上で非常に重要です。言葉の選び方や伝え方が子どもの心に与える影響は大きく、その良し悪しで子どものモチベーションや自己評価にも大きな違いをもたらします。
例えば、子どもがおもちゃの片付けを怠けている場面で、怒りや不安が湧いてしまうかもしれませんが、その時こそ冷静さを保つことが重要です。感情的にならずに、「お片付けをしっかりやることは大切なんだよ。この前、自分からお片付けをしてくれた時、かっこよかったな〜」というように、肯定的な言葉を使いつつ、ポジティブな方向に導いていくことが求められます。
ただし、肯定的な言葉だけを使うのではなく、具体的な改善点や理由を共有することも重要です。例えば、「お片付けをしないとお部屋がどんどん汚くなっちゃうよ。今日は時間をちゃんと計って取り組んでみよう」と具体的な指導を加えることで、子どもに行動改善の方向性を示します。
また、肯定的な叱り方では、子どもの気持ちや視点にも配慮することが重要です。例えば、子どもが失敗した時には、「今回はうまくいかなかったけれど、頑張ったね。次回に活かそうね」と失敗を前向きな学びの機会と捉えるように促します。子どもが自分自身を肯定し、成長できるような環境を提供することが目指されます。
さらに、肯定的な叱り方では、子どもの行動を叱るだけでなく、その行動の背景や理由にも焦点を当てます。例えば、「なぜそのように行動したのか理由を教えてくれると、ママももっと助けることができるよ」と理解を深めることで、子どもの自己肯定感やコミュニケーション能力を高める助けになります。
肯定的な叱り方を実践することで、子どもは自分の行動に責任を持ちつつも、自己評価を下げることなく成長できる場を提供されます。私たちは親として、子どものポジティブな発展を支援するために、言葉の力を大切に活用していきましょう。
私は、言葉を選んでいるうちに感情が爆発してしまうことがあったので、注意するときの肯定的な言葉掛けをメモしてラミネートしていました。頭で考えるよりも感情が先立ってしまう場合にオススメです。小さな心がけですが、子どもとの関係性に大きく関与していきます。
ラミネーターは高いですが、bonsaii ラミネーター A4 が今セール中で29%OFFでした。税込2,549円なのでかなり買い得だと思います。小学校受験のポスター作りなどにも活躍しましたので、よかったらチェックしてみてくださいね。
2. 行動を叱る、人を叱らない
叱る際には、その場の行動や行為に対して意見を述べるようにします。例えば、「机の上に散らかっているのはよくないね」というのは、その状況や行動に対する指摘です。一方で、「君がいつも散らかすから困る」というのは、その子の人格や性格に対する攻撃になりかねません。行動を改善するように促すことで、自己肯定感を保ちながら問題解決ができる環境を作り出します。
叱る際には、その場の具体的な行動や行為に対して的確に意見を述べることが重要です。例えば、「机の上に散らかっているのはよくないね」というのは、その状況や行動に対する客観的な指摘です。こうしたアプローチは、子どもに対して具体的な改善点を示し、問題解決の手助けをするものです。
一方で、「君がいつも散らかすから困る」というのは、その子の人格や性格に対する攻撃になりかねません。このような表現は、子どもが自己肯定感を失い、自己価値を貶めることにつながりかねません。代わりに、「机を片付けると、作業がスムーズに進むし、自分の物を見つけやすくなるね」というように、具体的な行動の影響や利点を伝えることが重要です。
叱る際には、その場の具体的な行動に対して注意を促すことで、子どもが自分の行動を改善しやすい環境を作り出します。また、行動を改善するように促すことで、子どもの自己肯定感を損なわずに、問題解決に向けたポジティブな成長を促します。このアプローチは、子どもが自分自身を肯定し、自己管理能力を高めるための重要な基盤を提供します。
親として、叱る際には言葉の選び方や表現方法に気を配ることが、子どもの心の成長と発達にとって重要です。具体的な行動にフォーカスし、建設的なフィードバックを通じて、子どもがより良い方向に向かうよう導いていくことが求められます。
3. 理由を説明する
子どもがなぜその行動が問題なのかを理解させることも大切です。理由を説明することで、ただ命令するのではなくその背景や意図を共有し、子どもがより意識的に行動できるようになります。例えば、「おもちゃを床に放置すると、誰かが転んでけがをする可能性があるから片付けましょう」というように、その行動がどのような影響を及ぼすかを説明します。
子どもがなぜその行動が問題なのかを理解させることは、肯定的な叱り方の重要な要素です。単に命令を与えるのではなく、その背景や意図を共有することで、子どもが行動に対する意識を深め、自己管理能力を向上させることができます。
例えば、子どもがおもちゃを床に放置した場合、「おもちゃを床に放置すると、誰かが転んでけがをする可能性があるから片付けましょう」というように、その行動が他者に与える悪影響やリスクを説明します。このように具体的な例を挙げることで、子どもが自分の行動が社会や他人に与える影響を理解しやすくなります。
また、理由を説明することで、単なる規則や命令の従属ではなく、なぜその行動が重要なのかについて理解する機会を提供します。例えば、教室での静かな態度の重要性を説明することで、「静かにすることで、他の子どもたちも授業に集中でき、先生も授業をしやすくなるんだよ」というように、その行動が学習環境に与える良い影響を示します。
さらに、理由を説明することで、子どもに対してリスク管理や社会的責任の概念を教えることもできます。例えば、「遊具で暴れると、他の子がけがをするかもしれないから、みんなが安全に遊べるように注意しようね」というように、安全性や協力の大切さを示すことができます。
このようにして、子どもが自らの行動を客観的に評価し、他者と共存するための適切な行動を選択できるようになるのです。理由を説明することで、単なる命令や禁止の枠を超えて、子どもが持つ可能性や自己肯定感を育む支援を行うことができます。
4. 目の高さで話をする
叱る際には、子どもの目の高さで話をすることが大切です。その方が子どもはより真剣に聞き入ってくれるし、尊敬されたと感じやすいです。その際に、感情の高ぶっている場面で叱ると、子どもが萎縮してしまうこともあります。落ち着いた状態で話をするようにすることが重要です。
叱る際に子どもの目の高さで話をすることがなぜ重要なのか、その理由を深く考えてみましょう。子どもの目の高さで話をすることは、コミュニケーションの質を高め、子どもが真剣に聞き入ってくれることを促進します。このアプローチは、子どもが自分の感情や考えを尊重されていると感じ、より建設的に行動するきっかけにもなります。
感情の高ぶった状態で叱ると、子どもが怯えたり、萎縮してしまうことがあります。特に小さな子どもたちは、大人の怒りや不安な表情に敏感に反応します。そのため、叱る際には落ち着いて冷静な状態で話をすることが重要です。子どもに対して安心感や信頼を与えるためにも、静かで穏やかなトーンで接することが効果的です。
例えば、子どもがルールを破ってしまった場合、「今日は友達と遊ぶルールを守らなかったね。友達と遊ぶときは、お互いにルールを守って楽しく遊ぼうね」というように、穏やかにルールや行動の重要性を説明することができます。このようなアプローチは、子どもが自分の行動を振り返り、自己管理を学ぶ手助けになります。
また、感情の高ぶりが収まった後に、子どもとじっくりと話し合う時間を持つことも大切です。叱るだけでなく、なぜその行動が問題なのか、どうすれば改善できるのかを共に考えることで、子どもの理解力や自己調整能力を育むことができます。
子どもの目の高さで話をすることは、親や教育者にとって子どもとの信頼関係を築くための重要な方法です。子どもが尊敬され、自分の声や意見が重要だと感じることで、自己肯定感や自己価値感が育まれるのです。落ち着いた状態でのコミュニケーションを通じて、子どもが成長し、良い方向に向かうようサポートすることが、肯定的な叱り方の鍵となります。
5. 叱った後はフォローアップする
叱った後は、その後のフォローアップも忘れないようにしましょう。子どもがどのように改善しているかを見守り、その成長や努力を称賛することで、ポジティブなフィードバックを与えます。例えば、「前はよくおもちゃを放置していたけれど、最近はすぐに片付けてくれてありがとう」というように、肯定的な変化に対しても気づいて伝えることが大切です。
叱った後のフォローアップは、子どもの成長と自己肯定感を育む上で非常に重要です。叱った後も子どもを見守り、どのように改善しているかを確認し、その成長や努力を明確に認めることで、ポジティブなフィードバックを与えることが求められます。
例えば、子どもが以前はおもちゃを放置していたが最近は片付けるようになった場合、「前はおもちゃを放置してしまうことが多かったけれど、最近はすぐに片付けてくれるようになって本当に嬉しいよ。おかげで部屋がすっきりして、遊びやすくなったね」というように、具体的な変化に気づき、子どもが取り組んだ成果を称賛します。
フォローアップは単なる一時的な指導や叱りだけではなく、子どもが持続的に行動を改善し、良い方向に向かうように支援するための重要なステップです。例えば、学校での問題行動を叱った後は、子どもと一緒にその原因や背景を再確認し、次回同じような状況を避けるための戦略を考える時間を持つことが有効です。
さらに、フォローアップでは子どもが自分で気づいた成長や努力を認める機会も与えることが重要です。例えば、「今日の授業で、あなたの発言がクラスに笑顔をもたらしたよ。みんながあなたの考えを尊重していることを感じたかな?」といった具体的な肯定的なフィードバックを通じて、子どもの自信を育むことができます。
叱った後のフォローアップは、単なる問題解決だけでなく、子どもとの信頼関係を深め、共に成長していくための重要なプロセスです。子どもが自分の努力や成長を認識し、それが価値あるものであると感じることが、持続的な自己成長への動機付けとなります。親や教育者として、このようなフォローアップを通じて子どものポジティブな発展を促進することが、肯定的な叱り方の一環として重要です。
さいごに
子どもの自己肯定感を下げないようにするためには、叱り方にも工夫が必要です。肯定的な言葉を使い、行動を叱ること、理由を説明すること、目の高さで話をすること、そしてフォローアップを忘れないことがポイントです。これらの方法を通じて、子どもが成長するための自己肯定感を育むサポートができるでしょう。
私は特に、『理由を説明する』という項目を小学校受験対策中によく使っていました。行動観察のフィードバック、ペーパー試験の振り返りなどです。小学校入学後の今もこちらの方法をよく取り入れています。私たち親子に合った方法なのかもしれません。そのご家庭に合った方法があると思いますので、いろいろ試して見つけてみてくださいね。
また、いっときの感情に流されずに将来を見据えた行動も大切です。私は目標設定をするときに、自身の教育観を大切にしていました。ご家庭それぞれの教育観や志望校によって大切にする部分は違います。この機会に、ご家庭の大切にしている部分や志望校について改めて考えてみてくださいね。
志望校を選ぶときには 日本一わかりやすい小学校受験大百科 がオススメです。国立小学校のみ受験される方も、どのような学校があるのか知っておくと今後の判断材料にしやすいです。