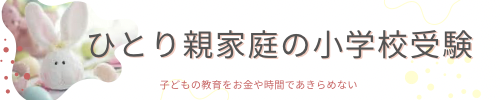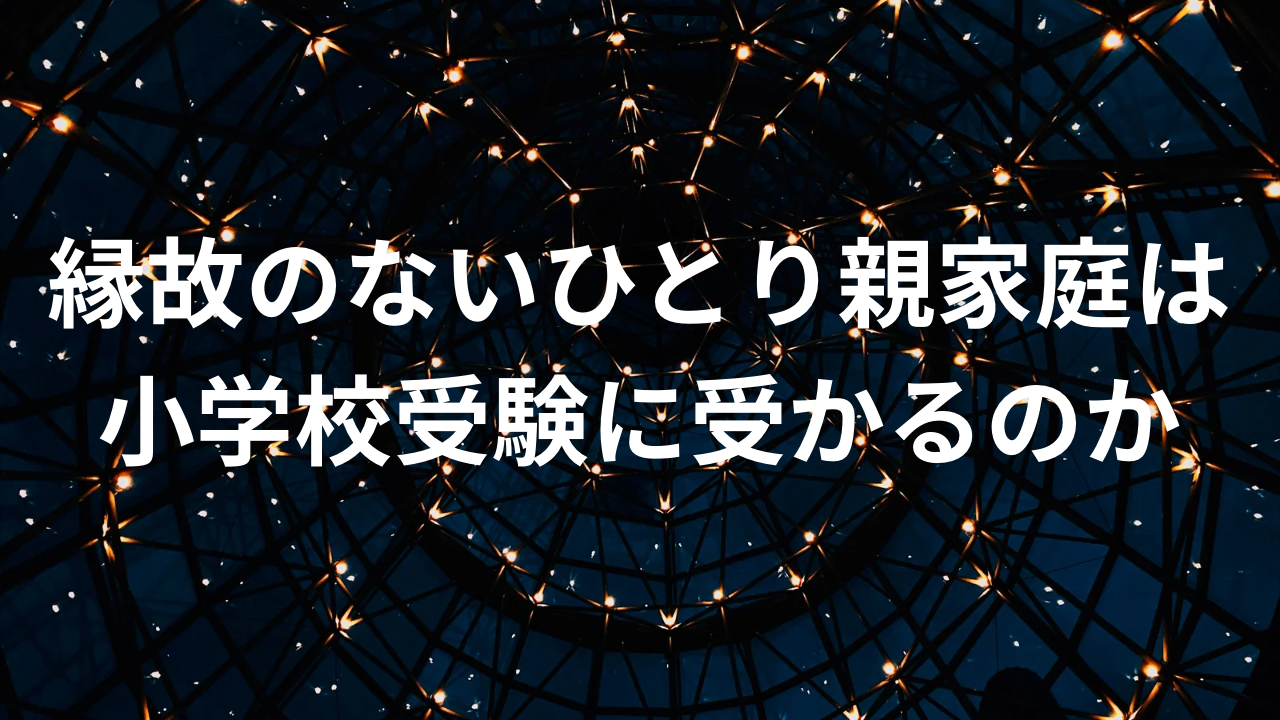この記事では、「小学校受験は縁故が必要だと聞いて不安に感じている」「小学校受験を考えているけれど、ひとり親家庭では厳しいのではないか」「わが子の環境をより良いものにしたい」と悩んでいる方向けに紹介します。
私自身がシングルマザーとして、わが子の小学校受験をサポートしてきた経験を持つ幼稚園教諭です。縁故も実家の援助もない中、仕事をしながら受験に挑みましたが、幸運にも全ての受験校から合格を勝ち取ることができました。小学校受験は親の受験と言われますが、その試験本番においては子どもたち自身が頑張るものです。親としての役割は、子どもの力を最大限に引き出すためのサポートであると信じています。このブログでは、ひとりのシングルマザーとしての小学校受験体験を率直に綴っています。実際の経験に基づいた内容ですので、全ての方に当てはまるとは限りませんが、同じような境遇の方々にとっては参考になるかもしれません。私がわが子の受験時に感じたように、ひとり親家庭の小学校受験に関する情報は限られていることから、このブログがお役に立てれば幸いです。
ひとり親家庭目線で国立小学校受験についてご紹介しますので、小学校受験について悩まれている方は参考にされてみてくださいね。
国立小学校受験について
国立小学校は実験校としての役割があり、大学と連携して研究を実践する場です。国の研究機関であるため、体験型授業や最先端授業を受けられます。教育熱心な家庭が集まるので学級崩壊のリスクも軽減できます。国立小学校受験では子どものありのままの姿が判断基準となります。なぜなら、優秀な生徒だけを集めてしまうと一般の小学校で研究結果を応用するのが難しくなるためです。そのため国立小学校受験では親の勤め先や役職などで判断されることはありません。
私立小学校受験との違い
全ての私立小学校ではありませんが、入学において両親共に健在であること、親の職業や御家柄が重要視される場合があります。公立小学校や国立小学校に比べて学費が高いため、6年間学費を支払い続けられる財力があるか見極める必要があるためです。そのためひとり親家庭では私立小学校に入学し辛いと言われてきました。国立小学校では親の職業や家柄ではなく、子ども本来の姿を見られるため、縁故など気にせず力を発揮することができます。
国立小学校受験を考える前に知っておくべきこと
国立小学校受験ではほとんどの場合抽選があります。考査に合格しても抽選を外してしまうと入学することができません。考査や抽選があるため兄弟で同じ学校に通えない可能性もあります。また通学範囲が定められているため、学区内に住居がないと受験することができません。学区外からでも合格後に引っ越しを確約できる場合は受験できる学校もあります。受験資格については各学校により異なりますので、お住まいの近くの学校を調べてくださいね。
ひとり親家庭の小学校受験について
小学校受験において私立小学校と国立小学校では大きな違いがあります。ひとり親家庭である場合、気になることは金銭面と縁故でしょう。ひとり親家庭の小学校受験についてここから詳しくお話します。
私立小学校の場合
私立小学校では繋がりを重要視している学校があります。その内容は、身内に卒業生がいる、兄弟がすでに通っている、附属幼稚園に通っている、推薦状を持っているなどです。これらは縁故と呼ばれるものです。私立小学校では独自の教育理念を掲げているため、同じ教育方針の家庭が集まります。私立小学校は学費も高額であるため、両親の職業や収入面を見られる場合もあります。ひとり親家庭であってもこの点がクリアしていれば合格する可能性があります。
国立小学校の場合
国立小学校に縁故はありません。私立小学校に比べて学費も安いため、収入面を気にしなくてもいいことがメリットです。しかし、合格をするためには準備が必要です。そのために受験塾へ通う家庭も少なくありません。受験塾の月謝の目安は2〜3万円程度です。季節講習や学校別模試などを受講すると年間数百万円かかることもあります。けれど、国立小学校受験では受験塾に通わず合格している家庭もあります。それは国立小学校が、幼児期を幼児らしく過ごした子どもを求めているからです。子どもと向き合い、日々の生活を丁寧に送ることで合格に近づけるでしょう。
国立小学校受験の際に気をつけること
国立小学校は公立小学校に比べて休みが多いです。先生が研究発表会へ行く場合などは自習時間になります。そのため教科書の内容が全て終わらずに学期末を迎えてしまう場合もあります。体験型学習など生徒にとって楽しい授業ではありますが、家庭学習が必須となる場合が多いでしょう。PTAや役員活動も盛んです。ひとり親家庭の場合子どもの休みに合わせて仕事を休む、学童を利用するなどしっかりと考えておく必要があります。
ひとり親家庭の小学校受験のメリット
小学校受験は親の受験と言われています。受験対策だけではなく、どのような育児をしているかがとても大切です。文部科学省で定められている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を通して、育児全般について詳しくお話していきますね。
文部科学省 幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/attach/1364730.htm
家庭内の教育方針をひとりで決められる
小学校受験の場合、家庭内の教育方針に一貫性があるかどうかが大切なポイントです。人格形成期にどのように過ごしたかは、今後の人生にも大きく影響します。適切なコミュニケーションをとることで相互に関連しながら総合的に発達していきますよ。発達段階に合っていない教育や子どもの自主性を重んじない育児では悪影響を及ぼす場合があります。我が子をみつめて、我が子にあった関わり方をすることは、小学校受験に関わらずとても大切なことです。家庭内の教育方針は、夫婦間で相違があることも少なくありません。我が子だけを見つめて家庭内の教育方針を自身で決められることはひとり親家庭のメリットでもあります。
文部科学省 子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/gaiyou/attach/1283165.htm
子どもの自立につながる
文部科学省の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の自立心の項目では以下のように記されています。
・自分のことは自分で行い、自分でできないことは教職員や友達の助けを借りて、自分で行う
・生活の流れを予測したり、周りの状況を感じたりして、自分でしなければならないことを自覚して行う。
・いろいろな活動や遊びにおいて自分の力で最後までやり遂げ、満足感や達成感をもつ。
子どもの自立心を育てるためには、適切に離れることも大切です。過干渉になりすぎると自立する機会を奪ってしまうかもしれません。成長に合わせて適切に関わりましょう。ママはやってくれるけどパパはしないなどのように一貫性がないと子どもは混乱してしまいます。一貫性を持って接することは大切です。
子どもとの関わり
ひとり親家庭では、育児と仕事を一人でこなさなければなりません。子どものことが後回しになって罪悪感を感じることもあるかもしれません。一緒にいる時間が短い、ついイライラしてしまうなどと考えることは、我が子を大切に思うからこそです。子どもとの関わりは時間の長さではなく、質の高さが大切です。教育方針や子育てについて一人で決められることは強みでもあります。子どもの環境をより良いものにしたいと考えることはとても素敵なことです。我が子をみつめて一貫性の持った育児をしてみましょう。それらができるのはひとり親家庭のメリットでもあります。
まとめ
これからひとり親として仕事を持ちながら小学校受験に挑む方は、不安に感じているかもしれません。国立小学校受験ではひとり親家庭であることは不利にはなりません。子どもが一人でいる時間が自立心を育み、成長することができます。子どもを尊重して接することでたっぷりの愛情をかけることもできます。縁故などに不安にならずに我が子をみつめて受験対策をされてくださいね。