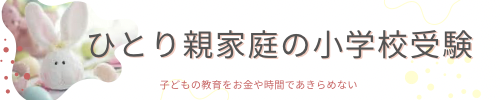行動観察は採点基準や合格基準が分かりづらいため、対策が難しいと思われるかもしれません。行動観察を学校が行う意味を考えると対策しやすいですよ。この記事では家庭でできる行動観察対策を詳しくお話ししますね。
- <目次>
- ◯国立小学校が行動観察をする理由
- ◯行動観察対策が大切な理由
- ◯家庭でできる行動観察対策
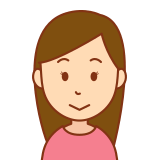
上記の内容をわかりやすく解説しますので、できるところから取り入れてみてくださいね。
国立小学校が行動観察をする理由
国立小学校は実験的・先導的な教育課題への取り組みに使命があります。大学・学部の教育実習の計画に基づく教育実習の実践を毎年行います。
つまり、その使命を果たすためには学級崩壊などは避けたいはずです。考査で行動観察を行う理由を詳しくお伝えしますね。
研究校である国立小学校が求めるもの
研究校である国立小学校では聞く力のある子どもを求めます。
また、勉学に意欲的な子どもも求められる傾向にあります。勉強を受動的ではなく、自ら学ぼうとする意欲が大切です。国立小学校では先進的な教育内容が行われるため、授業中の児童の反応や態度も研究内容としてみられるからです。
また、協調性がありコミュニケーション能力があることも大切です。一斉指導になることも多いため、聞く力や待つ力もみられます。
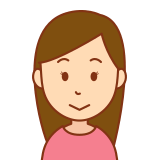
このような点から国立小学校では行動観察が行われているのだと考えられます。
国立小学校の考査内容
国立小学校の行動観察では他の受験生と一緒に遊んで、どのような振る舞いをするかがみられることが多いです。
ルールや勝敗のあるゲームからコミュニケーション能力などを確認されています。ルールを守ることはもちろん、負けたとしても勝った相手を賞賛することなどが大切です。
ルールは一般的なゲームから少し変更されていることがあります。「このゲーム知っている」と分かった気分になり、試験官の話を聞かずに行うと減点対象になります。受験生同士のコミュニケーションだけでなく、基本的なあいさつや指示をきちんと聞けるかどうかも採点基準となります。
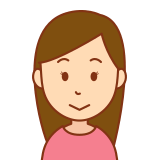
ゲーム性のあるものだけでなく、服をたたむ(生活習慣)、指示された工作をする(模倣課題)、指示された通りに運動する(サーキット)などもあります。志望校の過去問でどのようなことが求められているか確認しておきましょう。
行動観察対策が大切な理由
行動観察はほぼ全ての国立小学校で行われます。受験生同士のやりとりや協調性はもちろん、考査当日の全ての行動が見られていると言っても過言ではありません。
ルールを守ってゲームに参加するだけでは合格できないのが行動観察の難しいところです。どのような点に気をつけるといいか詳しくお話ししますね。
考査当日は全てが指示行動
考査日当日は全てが指示行動であると認識しましょう。
校門から入って出るまで意識を高めます。考査日はさまざまな場面で試験官の先生から指示があります。
「保護者と手を繋ぎましょう」のような指示も聞き逃さず、全てその通りに動きます。周りの人がしているからとその通りにすると間違った行動をしてしまう恐れがあるので注意しましょう。
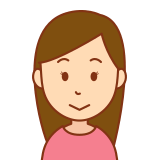
試験官の先生を目を見て話を聞くことも大切です。
日常生活があらわになる
学校の門をくぐると試験官の先生が立っています。保育園などで日頃から挨拶が習慣になっている子どもは元気よくあいさつをすることができるでしょう。
保護者の方に「ほら。あいさつは?」と言われてしまうと印象があまりよくありません。子どもは元気よくあいさつをしていても、保護者の方が会釈をする程度ということもたまにあるようです。保護者の方も試験官の先生の目を合わせてあいさつをしましょう。
就学前に身について欲しい事の一つにあいさつがあります。なぜあいさつをするのか、どのようなあいさつが好まれるかを子どもと一緒に考えてみるいい機会ですね。
また、靴の脱ぎ履き・脱いだ服を畳む・自分の物は自分で持つなども見られています。靴は立ったまま脱ぎ履きすることが望ましいです。座ったままだと体幹が鍛えられていないように見えるからです。
また、立ったまま脱ぎ履きすることで行動がスムーズになります。国立小学校では先生の指示を聞き、すぐに行動することが求められるため発達相応の機敏な動きが求められます。
行動観察ではゼッケンを着る場面もあります。脱いだあとはそのままにせず、畳むところまで採点されています。日頃から脱いだ服を畳む習慣がある子どもは手つきも慣れています。行動観察の対策として自宅で練習をしていても、長時間の考査になると忘れることもあるでしょう。
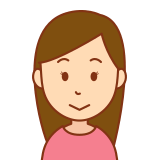
日頃から習慣化していくことが大切です。
家庭でできる行動観察対策
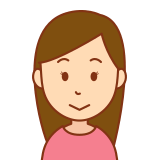
ここからは家庭でできる行動観察対策についてお話ししますね。
4〜5人子どもが集まって行うグループ行動観察は自宅での対策が難しいと言われてきました。しかし、行動観察対策講座をいくつもとると大変です。先ほども述べたように、日頃の行いがとても大切です。少しでも気になることがあれば試してみてくださいね。
指示行動
考査の日は学校の門をくぐった時から出るまで全てが指示行動だと思うようにしましょう。
楽しく折り紙をしている最中に、先生から小さな声で呼び出されて口頭試問が始まるといったこともあります。折り紙に夢中になりすぎて先生の指示を聞けないと減点対象になります。
いきなり難しい指示は子どもも混乱するのでまずは、お手伝いの中で練習をするといいですよ。
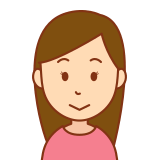
「靴下を畳んでね」「お箸を人数分並べたらコップを持ってきてね」このように1つの指示を聞けるようになったら指示をつなげてみましょう。
1つ目の指示は覚えているけど、次の指示を忘れていることがあります。他のことが気になってやらないかもしれません。「お箸を並べてくれてありがとう。つぎは何をするんだったかな?」と感謝の言葉を伝えながらお手伝いを促すと子どももやる気を出すかもしれません。
ここで大事なことは起こらないことです。お手伝いが辛いことと感じてしまうと続かなくなります。お手伝いは家族の一員であることを自覚する機会でもあるので、楽しみながら取り入れていきましょう。
2つの指示ができてら3つ4つと増やしていき、暗記力も高めていくといいでしょう。
お手伝いの中で指示を聞けるようになれば、次は遊びの中で試してみましょう。絵本を読んでいるときなどに「とうもろこしの皮を剥いてみない?」とお手伝いを頼んでみます。
このとき、絵本よりも楽しそうなお手伝いから始めてみましょう。子どもが少しでもめんどくさいと感じてしまうと「いやだ」と断られてしまうからです。楽しそうなお手伝いをしたあとはたくさん感謝の言葉を伝えて、次のやる気に繋げましょう。慣れてきたらお手伝いの難易度を少しだけ上げます。
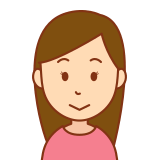
お手伝いをすると感謝されて嬉しい気持ちになることを知っていたら難易度を少し上げても手伝ってくれることでしょう。
このように少しずつ難易度を上げていき、考査と同じ内容のレベルまで持っていきます。ここで注意したいことは、子どもが本当に集中している遊びの時は声をかけないということ。遊びに没頭する時間も子どもには必要だからです。この練習は1日に多くても2回までがいいでしょう。
待機時間
考査中はさまざまな場面で待機時間があります。待機の姿勢も採点対象です。先生が見ていないと思って隣の子に話しかけてしまうと減点されてしまうので注意しましょう。
しかし、子どもが数時間静かにすることは難しいです。子どもの集中力は年齢+1分と言われています。
長時間にわたる考査では気が緩んでしまうこともあるでしょう。それは子どもらしい一面でもあります。
ここで大切なことは「あ!わたしいま気が緩んでいた!」と自分で気がつくことです。自分で気づけるようになるとまた集中することができます。
待機の姿勢の練習は数分から始めるといいでしょう。先ほども述べたように子どもの年齢+1分が集中力の時間です。
まずは、2分間の体育座りの練習から始めます。つい姿勢が悪くなったり、おしゃべりしてしまうこともあると思います。その様子を動画に撮って子どもと見返してみましょう。
どうしたらカッコいい姿勢になるか子ども自身が考えます。つい注意してしまいたくなりますが、子どもが自分で気づくことが大切です。1つでも改善策が見つかったら次の練習に活かしましょう。
しかし、待っている時間に子どもは忘れてしまいます。そのときは、壁に目標を貼ってみましょう。「しゃべらない」「ひざをくっつける」目で見ることで自分で気づく機会が増えていきます。子どもの成長に合わせて少しずつ練習時間をのばしていきます。
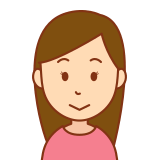
この練習は想像以上に疲れので、終わったあとはリラックスタイムを設けましょう。保護者の方も一緒にチャレンジしてみてください。子どもの努力が伝わると思いますよ。
グループ行動観察
自宅でする行動観察対策の中で一番難しいのがグループ作業ではないでしょうか。グループの行動観察は、勝敗のあるゲーム・協力するゲーム・共同制作などがあります。
年の近い兄弟がいても自宅で対策をするのは難しいかと思います。実際にゲームをすることは難しいですが、シミュレーションをすることはできます。
「こんなときどうする?」とお題を出して親子でディスカッションしてみましょう。「もしあなたのチームが勝ったら(負けたら)どうする?」「ゲームが始まったら最初にどんな声をかける?」このような質問をしてみることで、実際のグループ活動でも活かすことができます。
しかし、いきなりこのような質問をしても答えられないかもしれません。その場合は絵本を活用してみるといいでしょう。「あなたが登場人物ならどうする?」と読み聞かせをしながら問いかけることで、絵本の世界に入り込みシミュレーションがしやすくなります。
このとき、子どもの発言を否定せず受け止めることが大切です。否定してしまうと自分の意見に自信が持てなくなり、発言をしなくなる可能性があるからです。絵本の話をうまく繋げることが目的ではありません。
絵本のシミュレーションで慣れてきたら少しずつ行動観察の内容に近づけていきましょう。保護者の方が望む一声があるなら「こんな風に言うとどうかな?」と提案してみるのもいいでしょう。
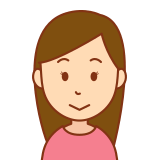
自分の発言に自信を持っていれば提案を受け止めて、次に活かすことができるかもしてません。子どもの自尊心を育てながら取り組んでいきましょうね。
まとめ
正答がわかりやすいペーパー問題と違い、行動観察はゴールが見えづらいところがあります。
過剰に対策をしてしまい、ロボットのような発言になってしまうこと…… そうならないためにも子どもらしさを尊重する必要があります。
志望する学校にもよりますが、国立小学校受験では過剰に対策しなくてもいいかと思います。
きらりと光る子を選ぶよりも、トラブルになりそうな子どもを避けるために見ているからだそうです。小学校受験対策に熱中しすぎて子どもの個性を奪ってしまうと元も子もありません。
どうして小学校受験をしようと思ったか改めて見つめ直すいい機会でもありますので、ゆっくり向き合ってみてくださいね。