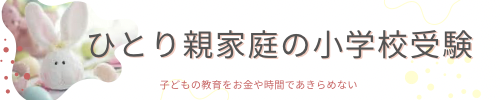ママ友から、よく「どうやって読書好きのお子さんになったの?」「普段どれくらいの本を読んでいるの?」と聞かれます。
私は子育てと仕事の両立をしながらも、自身の読書量は年間100冊程度をキープしています。お金と時間に限りがあるため、たくさんの本を買うことはできませんが、それでもわが子を読書好きに育てることができました。
この記事では、私がどのようにして子どもに読書の習慣をつけ、年間500冊もの本を読ませることができたのか、その具体的な方法を紹介します。読書は子どもの知識や想像力を広げ、学力向上にも大いに役立ちます。私と同じように限られたお金や時間の中で、子どもに読書の楽しさを伝えたいと考えている方々に、少しでもお役に立てれば幸いです。
それでは、さっそく本題に入りましょう。
子どもに読書の習慣をつける重要性
読書は、単に文字を読むという行為に留まりません。読書を通じて子どもたちは新しい世界に触れ、未知の知識や価値観を吸収し、想像力や思考力を鍛えることができます。また、読書習慣がある子どもは、学校の勉強や生活全般においても多くのメリットがあります。例えば、読解力の向上や語彙力の拡大は、国語だけでなく他の教科の理解にも大いに役立ちます。
さらに、読書は情緒や感受性の発達にも寄与します。物語を通じて他人の気持ちを理解し、共感する力を養うことができます。このような力は、対人関係の構築や社会生活を送る上で非常に重要です。
シングルマザーとして、時間やお金に制約がある中で、子どもに豊かな経験をさせることは容易ではありません。しかし、読書はそれを可能にする素晴らしい手段だと思っています。本は安価で手軽に入手でき、どこでも読むことができるため、限られたお金や時間を最大限に活用することができます。
私自身、子どもと一緒に読書の時間を共有することで、親子の絆も深まりました。読書は単なる学びのツールではなく、親子のコミュニケーションにもなります。この記事を通じて、私が実践してきた方法や工夫を共有し、皆さんのお子さんにも読書の楽しさを伝えるお手伝いができればと思っています。
読書好きになるための環境作り
子どもに読書の習慣をつけるためには、家庭での読書環境を整えることが重要です。まずは、家庭内での読書環境の具体的な方法をご紹介します。
1. 読書専用スペースの確保
読書に集中できる専用スペースを用意しましょう。このスペースは静かで落ち着いた場所が理想です。子どもがリラックスして本を読めるように、快適な椅子やクッションを置くと良いでしょう。また、明るい照明も大切です。自然光が入る窓辺や、適切な読書用ライトを設置することをおすすめします。
わが家は極狭物件ですが(笑)部屋の一角を読書スペースとしていました。部屋をまるまる用意できるといいですが、書斎を作る部屋数がありません。
しかし、部屋の一角を本棚で居心地の良い空間を作ると、自然とそちらに足が向かいます。「なんとなく居心地がいい」「ちょっと時間があれば、ここに行きたいな」そんな風に思える場所になれたら素敵だと思います。
わが子はその空間が好きすぎて、起き抜けに本棚へ向かっています(笑)
本棚 回転式 天然木は、省スペースでたくさんの本が入り便利です。

2. 本棚や本の整理
子どもが簡単に本を手に取れるように、本棚の高さを工夫しています。低い位置に本を置くことで、自分で本を選ぶ楽しみを感じられます。また、本をジャンルごとに分けたり、表紙が見えるように並べたりすることで、興味を引く本が見つけやすくなります。定期的に本を整理して、新しい本や子どもの興味に合った本を追加することも忘れないようにしています。

3. 読書をルーティン化する
毎日の生活の中で、読書の時間があります。例えば、寝る前の30分を読書タイムにする、朝食後に10分間読む時間を作るなど、日常の一部として読書を取り入れています。一定のリズムを作ることで、子どもは自然と読書を習慣として受け入れるようになりました。
4. 親の読書姿を見せる
子どもは親の行動を見て学びます。親が読書を楽しんでいる姿を見せることで、子どもも読書に対する興味を持ちます。親自身も読書の時間を持ち、家族で一緒に読書を楽しむ時間を作ることが大切です。親子で同じ本を読む、読み聞かせをするなど、読書を共有することで、読書が楽しい経験となります。
わが家は車を持っていないので、もっぱら公共交通機関を利用しています。電車やバスに乗る時は1冊ずつ本を持ち歩いています。隣に座っているママがいつも本を読んでいると、子どもも自然と本を読むようになりました。
電車やバスの中で静かに座っていてくれるので、一石二鳥です(笑)
また、後ほどご紹介しますがオーディオブックなどを利用することもオススメです。わが子は紙の本のみですが、大人はなかなか読書の時間を取ることができません……家事をしながらオーディオブックを聴いていると、それだけで子どもも本を手に取るようになりました。「ママの真似をしたい!」と思ってくれる時期に始めるのがいいのかもしれません。
ママの真似をしてお化粧したくなったり、お料理をしてみたくなったり。そんな時期がどの子どもにもあるのかなと思います。

5. 多様な本を揃える
子どもの興味を引くために、さまざまなジャンルやテーマの本を揃えています。絵本、物語、科学、歴史、漫画など、幅広い選択肢を用意することで、子どもは自分の好きな本を見つけることができています。新しい本やシリーズものを定期的に追加することも、読書の楽しみを続けるために有効だと思います。
本を選ぶのに悩んだ場合は、このようなサービスもオススメです。私は元々読書が好きですが、そうでないと本選びも大変かもしれません。本を選ぶことも時間がかかってしまいます。程よく力を抜いて、お金と時間のバランスを見つけてみてくださいね。

6. 図書館やオンラインリソースの活用
家庭内だけでなく、図書館やオンラインリソースも積極的に利用しています。図書館には無料で多くの本があり、子どもにとって新しい本と出会う絶好の機会です。また、私自身は電子書籍やオーディオブックを活用することで、場所を選ばずに読書を楽しむことができています。図書館のイベントや読書会に参加することも、読書への興味を広げる一助となります。
テレビをつけるのではなく、オーディオブックを聞くことで読書が当たり前の生活になっていきますよ。
これらの工夫を通じて、家庭内での読書環境を整え、子どもが自然と読書を楽しむ習慣を身につけることができるでしょう。
Kindle Unlimited 月額980円なら1冊読むだけでも元が取れます(笑)
Audible 普段あまり本を読まない方や時間が取れない人はこちらがオススメです。聞き流すだけでもなんとなく頭に入ってきて、気がついたら学習しています。
オーディオブックでオススメなのがハリーポッターシリーズです!読み聞かせをするのは大変だけど、ストーリが面白いので幼児でも楽しめました。寝る前の数分聞くだけで、傾聴力も高まったように思えます。
ハリーポッターの賢者の石なら1週間ほどで聞き終わりましたので、無料体験期間で楽しむことができます。一度楽しさを知って仕舞えば、あとは自力読みしてくれましたよ。

子どもが興味を持つ本の選び方
子どもが読書に興味を持つためには、年齢や興味に応じた本を選ぶことが大切です。以下に、年齢別のおすすめジャンルと、子どもの好みを見極める方法についてご紹介します。
オススメ知育絵本はこちらにまとめています。
年齢別おすすめのジャンル
0~3歳
絵本:色鮮やかな絵や簡単なストーリーが描かれた絵本は、視覚的な興味を引きます。
リズムや韻を楽しむ本:リズミカルな言葉や韻を踏んだ文章は、耳で楽しむことができます。
触れる絵本:触覚を楽しむための布や立体的な仕掛けがある絵本もおすすめです。
しましまぐるぐる 0さいからの知育遊び 絵本&にぎにぎマスコットセット

4~6歳
物語絵本:簡単なストーリーを持つ絵本が、物語の楽しさを教えてくれます。
アルファベットや数字の本:学びを取り入れた本が、文字や数字に興味を持たせます。
動物や自然の本:動物や自然に関する本は、好奇心を刺激します。

7~9歳
初めての読書本:短い章ごとに分かれた本や、イラストが多い本が、読書の楽しさを伝えます。
冒険やファンタジー:冒険物やファンタジーの物語は、想像力をかき立てます。
科学や歴史の本:簡単な科学実験や歴史の物語は、学びの楽しさを教えます。

自力読みできるようになったら
シリーズもの:続きが気になるシリーズものは、読書習慣を促進します。
ミステリーや探偵もの:推理や謎解きの要素がある本は、論理的思考を養います。
ノンフィクション:実際の出来事や人物についての本は、現実世界への興味を深めます。

子どもの好みを見極める方法
1. 観察と対話
子どもが日常生活で興味を持っていることを観察し、会話を通じて興味のあるテーマを把握しましょう。好きな動物や好きな遊び、興味を持っているテレビ番組などから、興味のヒントを得ることができます。
私は子どもとの会話をメモしています。会話の内容から次の本を選ぶことで、子どももより興味を持ってくれるようです。悩んだ場合は、とりあえず季節の行事関連の本がオススメです。季節ものは街中を歩いているだけで、たくさん目にすることができます。「この前見たやつだ!」「これ知ってる!」と少しでも興味を持ってくれると、本を手に取ってくれるかもしれません。
2. 図書館や書店での自由選択
図書館や書店に連れて行き、子どもが自分で本を選ぶ機会を作りましょう。自由に本を選ぶことで、自分の興味を見つけやすくなります。また、選んだ本を通じて、どのジャンルやテーマに興味を持っているかを知ることができます。
親が読んで欲しいと思う本と子どもが選ぶ本は大抵違います(笑)いろいろ言いたくなる気持ちをグッと堪えて、子どもが選ぶ本を尊重するようにしています。
けれど、たくさん本を買ってあげることもできません。できれば、長く使える本を選んで欲しいというのが本音です。
本屋さんに行くときは、あらかじめどんなジャンルの本を選ぶか親子で話し合っています。「この前、天気のことを知りたいって言ってたね」「あの物語の続き読みたい?」などと話しておくことで、ある程度選ぶ本の方向性を決めることができます。
本当は、好きな本を制限つけずに選ばせてあげたいのですが、時間と保管場所に制限があるので難しいですね。もっとお仕事を頑張って、子どもの興味関心にお金と時間をかけたいと思います!

3. さまざまな本を試す
さまざまなジャンルやテーマの本を提供し、子どもが興味を持つものを見つける手助けをしましょう。読み聞かせを通じて、子どもがどの本に反応するかを観察することも有効です。
子どもの興味関心から本を選ぶこともしますが、ジャンル問わずとりあえず読んでみることもしています。絵のタッチ、漢字の有無、本の大きさなど。どこで子どもの心を動かすかわかりません。
4. 学校や友達の影響を活用
学校の先生や友達が読んでいる本を参考にすることも良い方法です。同年代の子どもたちが楽しんでいる本は、自分の子どもにも興味を引く可能性が高いです。
保育園に置いてある絵本、小学校のオススメ図書などをチェックして家庭でも取り入れてみます。著者が同じ本を選んでみたり、同じテーマの本を選んでみたり。
わが子は国立小学校に通っていますが、本好きなお子さんは多いようです。子ども同士で好きな本を言い合い、それぞれ図書室で借りてきています。
5. 継続的な見直し
子どもの興味は成長とともに変わるため、定期的に本の内容やジャンルを見直し、子どもの成長に合わせて本を選び直すことが重要です。
本棚の配列を変えるだけでも効果はあるようです。まずはその時、興味のあるジャンルの本を、手に取りやすい位置に置くだけでOKです。
これらの方法を活用して、子どもが興味を持つ本を見つけ、読書の楽しさを感じられるようにしましょう。

読書習慣を身につけるための工夫
読書習慣を自然に身につけるためには、読書を楽しむ工夫と、毎日の読書タイムを設定することが重要です。以下にその具体的な方法をご紹介します。
1.本の内容を真似してみる
読んだ本の内容を真似してみます。例えば、物語の世界を模型で再現する、キャラクターのコスチュームを作る、またはストーリーを続けて書いてみるといったことです。これにより、物語に対する理解が深まり、読書がより魅力的な体験になります。子ども向けのレシピ本から実際に料理を作ることも楽しいです。レシピが載っている物語もあるので、本を読んだあと、実際に作るといいですね。
わが家が一番最初に作った絵本レシピはバムとケロのドーナツです。絵本に出てくるお料理って美味しそうですよね。
児童書になるともっと幅が広がります。こちらの本はレシピも載っているので、読んだあとも楽しめますよ。

2.定期的な読み聞かせタイム
親子で読み聞かせの時間を設けることで、読書が楽しい時間になります。親が積極的に物語を声に出して読むことで、子どもは物語の世界に入り込みやすくなり、感情豊かな読書体験ができます。
仕事で疲れて読むのがしんどい……という時もあると思います。そんな時は、YouTubeにストーリーテリングをアップロードしていますので、ご利用くださいね。
3.読書に基づくクイズやゲーム
読んだ本に基づくクイズやゲームを作成して、親子で楽しむことで、物語への理解を深めるとともに、読書の楽しさを増すことができます。例えば、「このキャラクターはどこに住んでいるか?」や「物語の中で何が起こるか?」といったクイズです。
4. 読書ノートやレビューの作成
子どもが読んだ本の感想やレビューを記録する読書ノートを作りましょう。これにより、物語の内容を振り返りながら、自分の考えや感想を整理することができます。また、読書ノートにシールやイラストを追加することで、楽しみながら記録を続けることができます。
5. 短い読書セッションからスタート
最初は短い時間から始め、徐々に読書時間を延ばしていきましょう。例えば、最初は10分間の読書タイムからスタートし、慣れてきたら15分、30分と時間を増やしていくと良いです。
6. デジタルデバイスの制限
読書タイムには、テレビやスマートフォンなどのデジタルデバイスを制限しましょう。これにより、読書に集中しやすくなります。また、デジタルデバイスの代わりに本を持つことにより、読書に対する専念が高まります。
7. 読書タイムの目標設定
読書タイムに具体的な目標を設定することで、モチベーションを高めることができます。例えば、「1週間に1冊読む」「毎日10ページ読む」といった目標を立て、達成するごとに小さなご褒美を用意すると良いでしょう。
これらの工夫を取り入れることで、子どもが読書を楽しみながら、自然に読書習慣を身につけることができます。

親子で一緒に楽しむ読書
親子での読書は、親子の絆を深め、子どもの読書習慣を育むための貴重な時間です。以下に、読み聞かせの効果と方法、そして親子での読書ディスカッションのポイントをご紹介します。
1. 語彙力と理解力の向上
読み聞かせを通じて、子どもは新しい語彙や表現に触れ、理解力を高めることができます。豊かな言葉の世界に触れることで、語彙が自然に増えていきます。
2. 感情の理解と共感の育成
読み聞かせは、物語の登場人物の感情や行動を通じて、子どもに共感の力を育てます。物語に登場するさまざまな感情や状況に対する理解が深まります。
3. 集中力の向上
読み聞かせの時間は、子どもが物語に集中し、注意力を養う良い機会です。特に感情豊かに読むことで、物語に対する興味が高まります。
4. 親子の絆の強化
読み聞かせは、親と子が一緒に過ごす時間を提供し、コミュニケーションを深める助けになります。親が積極的に関わることで、子どもは安心感を持ち、読書が楽しい時間になります。

読書の成果を振り返る
読書の成果を振り返ることは、子どもがどれだけ成長したかを確認する良い機会です。以下に、読書記録の活用方法と、子どもの成長と変化を感じるポイントをご紹介します。
1. 読書ノートの作成
内容の記録: 子どもが読んだ本のタイトル、著者、読了日などを記録するノートを作成します。これにより、読んだ本を一覧で確認でき、読書の履歴を視覚化できます。
感想の記入: 各本についての感想や印象を書き込むページを設けると、読書後の理解を深める助けになります。子どもがどの部分に感動したのか、どのキャラクターが気に入ったのかを記録することで、物語への関心が高まります。
2. 読書チャートの作成
読書量の視覚化: 読書量を視覚的に確認できるチャートを作成するのも効果的です。例えば、月ごとに読んだ本の数を記録するグラフや、年間の読書目標に対する達成度を示すチャートです。目に見える形で成果を確認できると、モチベーションが高まります。
3. 定期的な振り返り
振り返りの時間を設ける: 定期的に読書記録を振り返る時間を設け、読んだ本やその感想について話し合うことが重要です。たとえば、月末にその月に読んだ本について振り返り、感想を共有することで、子どもは自分の成長を実感できます。
目標の見直し: 読書の目標や計画を定期的に見直し、必要に応じて調整します。達成した目標を確認し、新たな目標を設定することで、読書の習慣をさらに定着させることができます。

図書館やオンラインリソースの活用
図書館は、子どもが読書に親しめる素敵な施設です。以下に、それぞれの活用法をご紹介します。
1. 図書館カードの取得と利用
図書館カードの取得: まずは地域の図書館で図書館カードを取得しましょう。図書館カードがあれば、館内の本を自由に借りることができます。
子どもの名前で作ること子どもは喜んでくれます。
貸出制度の活用: 図書館では多くの本を借りることができるため、様々なジャンルやシリーズを試す良い機会です。子どもと一緒に借りる本を選ぶ楽しみを共有しましょう。
2. 図書館のプログラムやイベント
読み聞かせイベント: 多くの図書館では、子ども向けの読み聞かせイベントやストーリーテリングなどを開催しています。参加することで、読書の楽しさを体験できます。
図書館主催のワークショップ: 創作活動や読書関連のワークショップが開催されている場合もあります。これに参加することで、読書に対する興味がさらに深まります。
3. 図書館のサービス
リクエスト制度: 図書館にない本でも、リクエストを出すことで取り寄せてもらえることがあります。興味のある本やシリーズがあれば、リクエストしてみましょう。
図書館のウェブサイト: 図書館のウェブサイトでは、オンラインで蔵書の検索や予約ができます。自宅からでも新しい本を探して予約することができ、便利です。
4. 定期的な訪問
定期的に図書館を訪れることで、最新の本やイベントをチェックし、子どもと一緒に読書の時間を楽しむ習慣を作りましょう。

継続するためのモチベーション維持
読書習慣を継続するためには、モチベーションを維持する工夫が重要です。以下に、目標設定と達成の喜びを感じる方法、そして他の親子との交流の方法をご紹介します。
年間読書目標の設定: 年間で読んでみたい本の数や、特定のジャンルに挑戦する目標を設定します。例えば、「今年は12冊の科学本を読む」など、具体的な目標を立てると達成感が得られやすくなります。
短期的な目標の設定: 月ごとや週ごとに小さな目標を設定することで、達成感を積み重ねやすくなります。例えば、「今月は3冊の本を読む」といった短期的な目標です。
1. 進捗の記録とレビュー
読書記録の活用: 読んだ本を記録することで、自分の進捗を可視化できます。読書ノートやアプリを利用して、達成した本や目標の進捗をチェックしましょう。
定期的な振り返り: 定期的に読書の進捗を振り返り、目標達成度を確認します。達成した目標や読んだ本のリストを見返すことで、達成感を感じることができます。
達成感を味わう: 目標を達成した際には、自分や子どもに対して小さなご褒美を用意することで、努力の成果を実感できます。例えば、新しい本を買う、特別な読書タイムを設けるなどの方法です
おわりに
読書は子どもの成長にとって重要な要素であり、知識の拡充や感受性の育成、思考力の向上に大いに貢献します。これからも読書を通じて子どもが楽しく学び、成長できる環境を整えていきたいと思います。
このブログでご紹介した方法や取り組みで参考になるところがあると嬉しいです。子どもが読書を楽しむ環境を整え、習慣を育んでいくことができれば、長期的な読書の楽しさと成長を実感できるでしょう。読書は単なる知識の習得にとどまらず、子どもの人生における貴重な財産となります。
これからも子どもと一緒に読書を楽しみながら、成長を支えていくことを目指していきたいです。共に素晴らしい読書の旅を続けていきましょう。